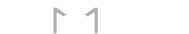【座談会】「思考調達」によるイノベーション創出 ~企業とアカデミアの新たな関係が未来を拓く~
2025年 10月 29日
<登壇者>

古谷 紳太郎:COMMONZ株式会社 代表取締役副社長。本稿で説明する「思考調達」の提唱者。

宮野 公樹:京都大学 学際融合教育研究推進センター 准教授。一般社団法人STEAM Association代表理事。

伊藤 義訓:元アサヒビール株式会社 常務取締役。現COMMONZ株式会社 シニアアドバイザー。思考調達プロトタイピング時の経験者。

宮田 慎吾:キッコーマン株式会社 おいしさ未来研究センター 情報解析グループ。思考調達サービス利用者。
はじめに
企業の持続的な成長にイノベーションが不可欠とされる現代、その源泉としてアカデミアとの連携(産学連携)に多くの期待が寄せられています。しかし、「共同研究」や「技術指導」といった従来の枠組みだけでは、ゲームチェンジにつながるような真のパラダイムシフトを起こすことは難しいのが現状です。
なぜ、イノベーション創出を狙った産学連携はしばしば期待外れに終わるのか。企業とアカデミアの間にある壁は、どうすれば乗り越えられるのでしょうか。
COMMONZはその問いに対する一つのソリューションとして、産学連携の新たなアプローチ「思考調達」を提唱します。これは、単なる知識や技術の「導入」ではなく、学術的な「思考」そのものを企業の活動に取り入れ、新たな価値創造を目指す試みです。
本記事では、「思考調達」の提唱者、アカデミアから越境を目指す学者、そして実際に思考調達を体験した企業の実践者、それぞれの立場から、その本質と可能性、そして産学連携が抱える根深い課題について、率直に語り合います。
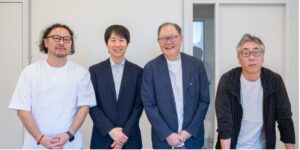
第1部:思考調達とは何か?
~「導入」ではなく「調達」である理由~
古谷: まず「思考調達」の定義からお話しします。これは、調査や分析といったアカデミアの「機能」を調達するのではなく、アカデミックなアプローチ・方法論すなわち「思考」そのものを調達し、企業活動のパラダイムシフトを狙う活動です 。「機能」ではなく「思考」という点が大事なポイントですが、ポイントはもう一つあって、「導入」ではなくあえて「調達」という言葉を使っている点です。
伊藤: 「導入」と「調達」は全く違います。例えば、ある役割やスキルを持つ人材を、そのまま組織に「ぱかっ」と当てはめるのが「導入」です。しかし、鍵と鍵穴のようにぴったり合うことはまずありません。そこで必要になるのが、単なる言葉の置き換えである「通訳」ではなく、文脈や背景を汲み取った「翻訳」ですね。
古谷: その通りです。例えば、「任天堂Wiiの開発で文化人類学者が活躍したらしい。じゃあ、うちの開発チームにも文化人類学者を入れればいいものができるだろう」といった安易な発想が「導入」の典型です。しかし、異物が入れば拒絶反応が起きるのが自然で、これではうまくいきません。過去には、ある大企業に哲学者が一度に大勢投入されたものの、数年で全員いなくなってしまったという話も聞きます。
伊藤: こうした産学連携の難しさの根底には、根深い認識のズレがあります。以前、ある国立大学の学長が「大学は企業の下請けじゃない」と言い切ったそうです。これは、企業側が大学を便利な「機能」としてしか見ていないことへの反発でしょうが、対話の入り口から閉ざしてしまっている。一方で企業も大学のことを知らなすぎる。この相互不理解が、多くの産学連携を形骸化させています。
古谷: 「思考調達」がそうした「導入」と一線を画すのは、アカデミアを幅広くカバーしかつビジネスの文脈がわかる人材-弊社では「キュレーター」と呼んでいます-が、以下の2つの重要なプロセスを担っているからです。
1.調達する思考の「選択」:
特定の専門分野に閉じこもらず、常に外の世界に興味関心が広がり(点ではなく面で捉え)、専門に閉じた「研究者」ではなく越境するマインドを持った「学者」を厳選します。
2.調達した思考の「翻訳」:
その学者に丸投げして思考や言葉をクライアントにそのまま伝えるのではなく、企業側の文脈で価値が生まれるように「翻訳」し、着地させます。
この2点があることで、専門外のことは「分かりません」で終わってしまうような空回りを防ぎ、企業が「どう受け止め、どう活かせばよいか」まで落とし込むことができるのです。
第2部:思考調達のメリット①
~企業の視点:「バイアスの破壊」と「熱意の種」~
伊藤: 企業、特に大企業にいると、どうしても過去の成功体験や自社の常識といった「バイアス」の延長線上で物事を考えてしまいます。私自身、研究所からマーケティング部門に異動した当初、「マーケティングにロジックを導入してやる」と意気込んでいました。しかし1年経って、特に嗜好品の世界では「それはやってはいけないことだ」と痛感したのです。理屈で買わないものを、理屈で売ろうとしていたわけです。
思考調達は、この自分たちでは壊せないバイアスを破壊する、強力なきっかけになります。全く関係ないと思っていた他分野に広がる思考に触れることで、自分たちが囚われていた常識にハッとさせられるのです。
宮田: とてもよく分かります。自社や業界の考え方だけでは、どうしても停滞感が出てきます。「ある程度進めてみたけれど、踊り場にいるな」と感じる時に、思考調達は新しいジャンプを可能にする「バネ」のような役割を果たしてくれました。自分が認識すらしていなかった世界から新しい視点を取り入れることで、組織の頭が整理され、新しい道筋が見えてくる感覚です。
伊藤: もう一つ重要なのは、イノベーションの源泉となる「熱意と情熱」の発見です。企業では、新しい企画を通すために膨大な「理論武装」に時間を費やしがちです。しかし、本当に人を動かし、前例のないことを成し遂げるのは、理屈を超えた「これをやりたいんだ」という内発的な熱意です。
宮野: 私が大学で企業のエグゼクティブ向けに講義をすると、彼らが最も感動するのは、研究内容の凄さ以上に「先生たちの熱意がすごい」という点なんです。ミミズの研究に人生を捧げるような、一つのことを突き詰める熱量に心を揺さぶられる。企業では、日々の業務の中でそうした純粋な熱意に触れる機会が少ないのかもしれません。
伊藤: まさにその通りで、思考調達は、その「熱意の種」を見つけるプロセスでもあります。そして、その種を顧客との対話を通じて「ナラティブ」(顧客自身の物語)として育てていくことが、今の時代のマーケティングでは不可欠です。例えば、自動車業界でもBMWは「駆け抜ける歓び」という情緒価値を訴求し、スペックを声高に語りません。
アサヒビールの商品開発でも、思考調達を通じて心理学の専門家など異分野の思考に触れた経験があります。そこから直接的な答えが見つかるわけではありません。しかし、対話を通じて「嗜好品の本質はスペックではなく情緒であり、その価値はお客様自身が作る物語にある」という確信を得ました。
スペック競争から抜け出し、「日本の皆様おつかれ生です。」という情緒に訴えるコミュニケーションが生まれた背景には、こうした思考調達による気づきがありました。ちなみに、「日本の皆様おつかれさまです」では表現の自由度が高すぎて、飲み物の文脈に落ちない。「おつかれ生です」とすることで、ビールを介したコミュニケーションとして顧客に認識されたのです。
宮田: 通常の有識者ヒアリングでは、話を聞いて「面白かったね」で終わってしまうことがほとんどです。それは、聞いた話を「どう自分たちの文脈に接続するか」というスキルが企業側に求められるからでもあります。思考調達では、その最も難しい部分をキュレーターが伴走してくれる。だからこそ、聞いた話が自分の中で消化され、自社の取り組みをドライブさせる「熱意」にまで昇華されるのだと感じています。

第3部:思考調達のメリット②
~アカデミアの視点:「自信の回復」と「新しい評価軸」~
宮野:次にアカデミア側の意義ですが、一言でいうと、研究者の「自信回復」、あるいは「ケア」につながる点が大きいと感じています。今の学会発表は、本質的な対話というより、いかに批判されないかという「ディフェンス」の側面が強い。査読はブラインドで叩かれるのが基本で、褒められる機会は極めて少ない。
昔のお坊さんが村の知恵袋として頼られたように、かつて大学の先生は社会の拠り所でした。しかし今は専門分化が進み、社会から隔絶され、どこか「拗ねている」状態に陥りがちです。思考調達は、そんな研究者たちにとって、自分の問いや研究が、全く想像しなかった分野で社会の役に立つという喜びを与えてくれます。「自分のやっていることには、こんな価値があったのか」と再認識できることは、研究を続ける上で大きな自信になります。私が主宰する「3-Questions」というイベントでは、分野を問わず匿名で本音の対話をしますが、企業の方や一般の方から「面白い」と言われることが、研究者にとって大きな励みになっています。
古谷: 自分の問いの意義を、狭い専門分野の中だけでなく、広い社会の中で確認できるわけですね。
宮野: そうです。そして、それは新たな問いの発見にもつながります。さらに大きな視点で見れば、アカデミアの「新しい評価軸」を生み出す可能性も秘めています。今の大学、特に人文社会系では、科学主義へのコンプレックスからか、自ら「人文科学」などと名乗り、理系の評価基準に合わせようとして、本来の価値を見失っている側面があります。
古谷: 「論文を何本生産したか」というKPI(重要業績評価指標)がその典型ですね。
宮野:まさにそうです。論文を書くこと自体が目的化し、中身が問われなくなっている。それではイノベーションの源泉にはなり得ません。思考調達を通じて企業や社会に貢献した実績が、論文の数とは別の、研究者の新しい評価軸の一つになれば、アカデミアはもっと活性化するはずです。これは、この活動が持つ「隠れミッション」でもあります。
おわりに:共創の未来へ ~3つの鍵とキュレーターの役割~
伊藤: ここまでの議論を整理すると、思考調達が機能するには3つの鍵があると思います。
1.バイアスの破壊:まず、自社の常識から離れた異分野の思考に触れ、自分たちの「コンピテンシートラップ」(過去の成功への固執)から抜け出すことが必要条件です。
2.翻訳と伴走:しかし、それだけでは「良い話を聞いた」で終わってしまう。得た知見を自社の文脈に「翻訳」し、プロジェクトをドライブさせるキュレーターの伴走が不可欠です。
3.出会いのコーディネート:そして最も重要なのが、どの企業のどの課題に、どの学者の思考を掛け合わせれば化学反応が起きるかを見極める「人選び」です。この出会いをコーディネートすることこそ、キュレーターの真骨頂と言えるでしょう。
宮野: まさに、その「キュレーター」をもっと増やしていくことが、今後の日本にとって重要ですね。
古谷: おっしゃる通りですね。そういう意味では、いずれ全ての企業や大学が自前で思考調達のような活動ができるようになり、熱量を取り戻した企業がどんどんイノベーションをけん引する…そんな世の中になって、私たちの仕事がなくなる方が良いんじゃないかと思ったりもします。しかし現実的には、人も組織も万能にはなれません。専門分化が行き過ぎると元の木阿弥になりますが、やはりそれぞれの立場を活かした「役割分担」は重要でしょう。そこで、私たちはまず日本企業が熱量を取り戻すためのモデルケースを作り、産学連携の新しい成功事例を社会に示していきたいと思っています。
この対談が、モデルケース作りに参加したいと思って頂ける企業を一社でも増やし、アカデミアでくすぶっている学者たちに少しでも希望を与えることができれば幸いです。